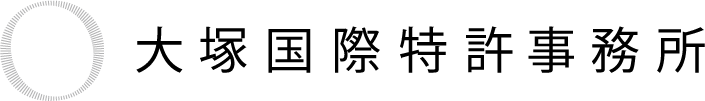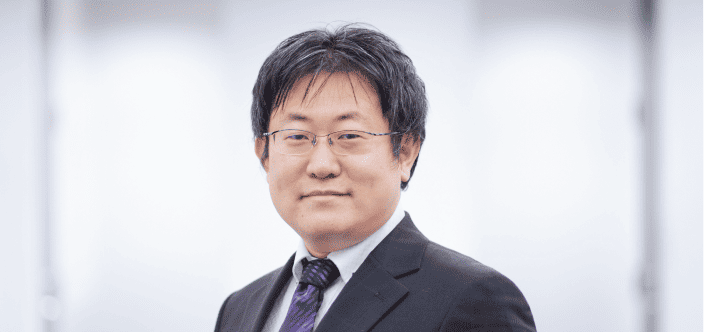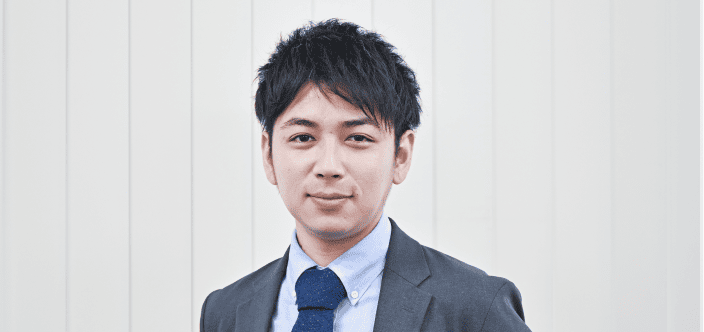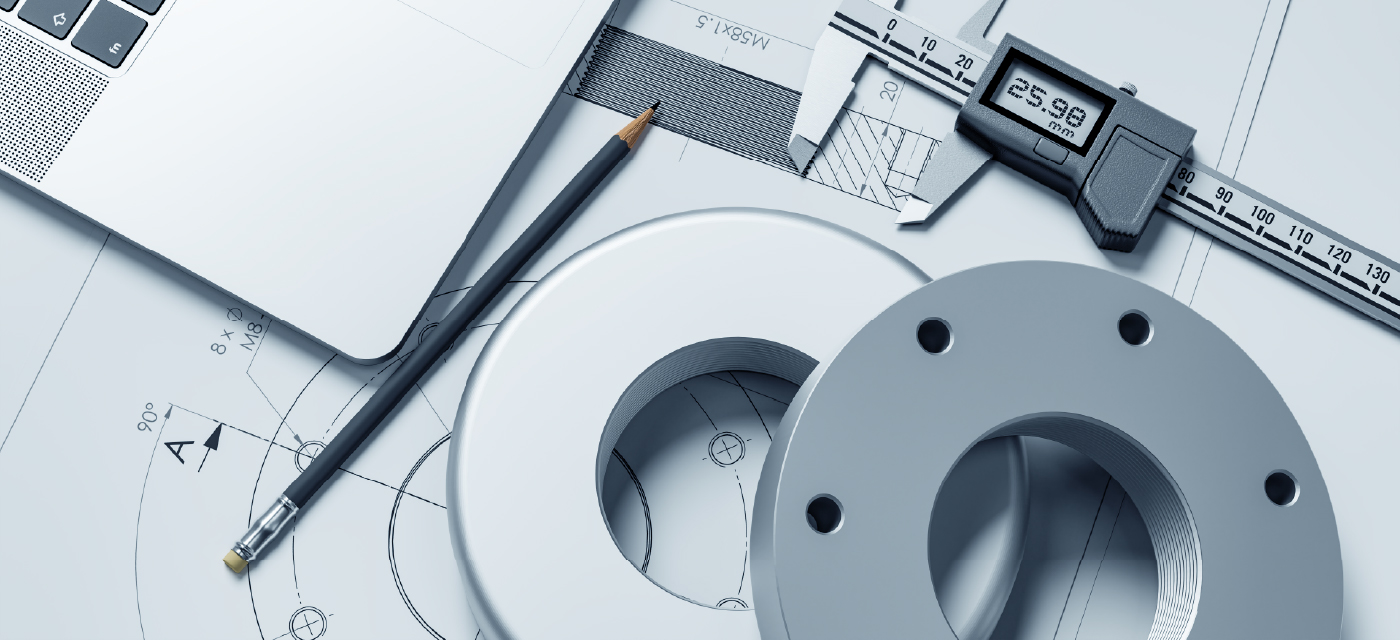所員インタビュー
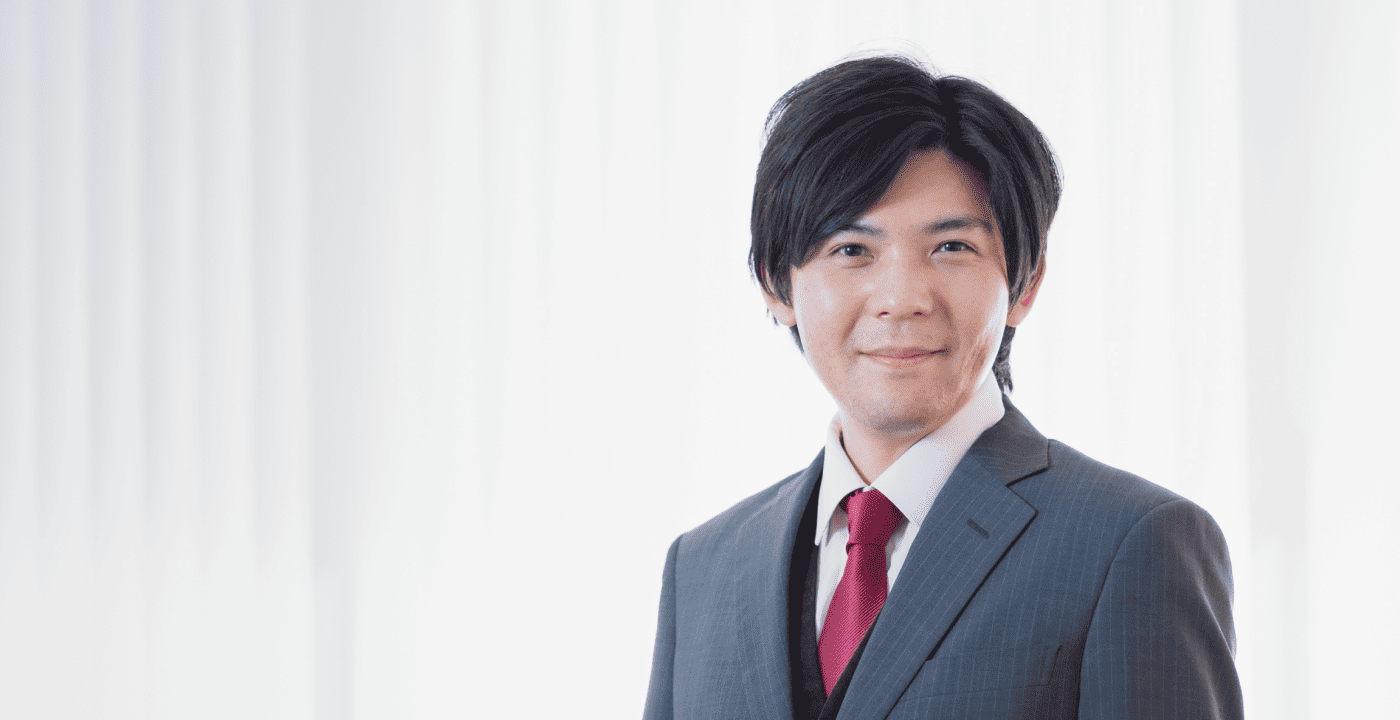
Hideo Sugawara
-
弁理士を目指されたきっかけは?
2009年に大学院を修了する前の就職活動を通じた選択でした。当時は事業会社で働く道も考えていたのですが、一つの会社で研究開発職として地道に技術や製品の改良を続けていく仕事が、自分に務まるのだろうかという迷いがありました。私の場合、一つのことをずっとやるより、新しい技術に触れ、その本質を理解していく方が向いているなと思っていました。
弁理士という職業は、発明にストーリー性を持たせ、特許出願をドラフティングすることが主な仕事ですが、最初から最後まで自分で完結させられる、また、完結したら別の仕事を担当できる、という働き方の専門職ですので、自分にはこっちのほうが合っていそうだな、と魅力を感じたんです。 -
大塚国際特許事務所を選ばれた理由を教えてください
事務所見学の際、特に印象的だったのは雰囲気ですね。オフィスを見せていただいて、穏やかだなと感じました。皆さん、わりと淡々と仕事をされているんですよね。私も仕事は論理的に効率的に進めるのが好きなので、技術文書を作成する際に必要な集中力が得られる環境だと感じました。
もう一つ、基本給にプラスして成果ベースがある給与制度も魅力でした。成果給については、自分の売上に連動しますし、自分でも計算できるので明確です。頑張った分、ちゃんと返ってくる、というフィードバックがはっきり見えます。仕事がどれだけ上達したかが可視化できてモチベーションに繋がります。 -
日々の業務はどのように進められているのでしょうか?
基本的に出願の準備、その追行の仕事がメインです。弁理士は技術を理解し、その為には集中できる環境が何より重要です。働く時間帯は人によって様々ですが、私は、今は朝型の働き方をしています。7時20分にオフィスに着いて、7時半から仕事を始める。朝9時の始業開始までの時間が特に快適ですね。
この時間帯は事務スタッフや技術スタッフとのやり取りも少なく、書面作成に集中できます。9時以降は様々なコミュニケーションが発生するので、どうしても、複数の作業を並行して行う必要があります。だからこそ、この早朝の静かな時間を大切にしています。
また、週のリズムづくりも工夫しています。月曜と火曜は朝から集中的に書類を作成し、水曜は、午前中は在宅勤務を活用して少しペースを落として、午後からオフィスでまた集中して働く、という形でメリハリをつけています。 -
15年のキャリアの中で、実感された成長は?
大きく3つの段階がありました。最初の5年間は基本的な業務の習得期間です。技術を自分の言葉で表現できるようになった、その手応えを実感したのが5, 6年目頃でした。クライアントから頂戴する提案書が無くともゼロから出願書類を作成できるようになり、大きな転換点となりました。
次の5年間は、処理できる案件数が増え、効率や生産性を向上させることができました。ライフステージの変化もあり、自分なりのペース配分を確立していった時期です。
ここ最近の3年は、さらなる上達を実感しています。以前に比べて、かなり効率よく出願書類を作れるようになっている。15年経っても、まだ上手くなれるんだという発見があって、良い仕事だなと感じますね。 -
担当される技術分野について教えてください
私が大学院で研究していた当時は、機械工学分野で、流体力学のシミュレーションなどが専門でしたが、現状は、自分の研究領域そのものずばりの技術を扱うことは全くありません。私は、「どんな技術であっても、振られた仕事に関してはノーと言わない」というのを信条としています。その都度、新しく勉強する必要があるのは大変ですが、面白みでもあります。また、事務所には、技術開発に携わったリアルな経験を持つ方が多数おりますので、同僚、先輩から生の技術を学べる環境にあり、新たな分野に自信を持って進めます。
理系のバックグラウンドのおかげで、数式やロジックの理解がしやすいというのは当然ありますが、出願書類において技術説明をするためには、いかに具体的に想像できるかというのが重要なので、OJT(on-the-job-training)で実際に手を動かさないと学べない部分も多いですね。
この点、研究開発の現場を知っていらっしゃる方は、弁理士や技術スタッフとして仕事をする上で、大きな強みになると思います。私の場合は、事業会社での経験がなく、大学院を卒業してからすぐ入所したので、技術の具体的なイメージを想像するのに大変さがありました。そこは、クライアントの工場に伺ってお話をお聞きするといった形で補ってきました。 -
働き方の面ではいかがでしょうか?
在宅勤務は助かっています。週1回の在宅勤務ができます。この制度で1週間の中で働くリズムを作れ、自分の都合に合わせて在宅勤務を設定できます。この仕事は期限管理がきわめて重要なので、計画性と柔軟性を両立させることができる環境は良いですね。
-
これから弁理士・技術スタッフを目指す方へのメッセージをお願いします
この仕事の面白さは、技術を言葉で表現するという知的な挑戦にあります。技術の本質を理解し、それを論理的な文章として紡いでいく。その過程で、理系のバックグラウンドは確実に活きてきます。
特に印象深いのは、経験を重ねるほどに上達を実感できる点です。より良い表現方法が見つかったり、作業の効率が上がったり。そして、その成長は数字として明確に見えます。頑張った分だけ確かな手応えが得られ、それが報酬にも反映される。技術への探究心と、それを言葉にする喜びを存分に味わえる仕事だと思います。